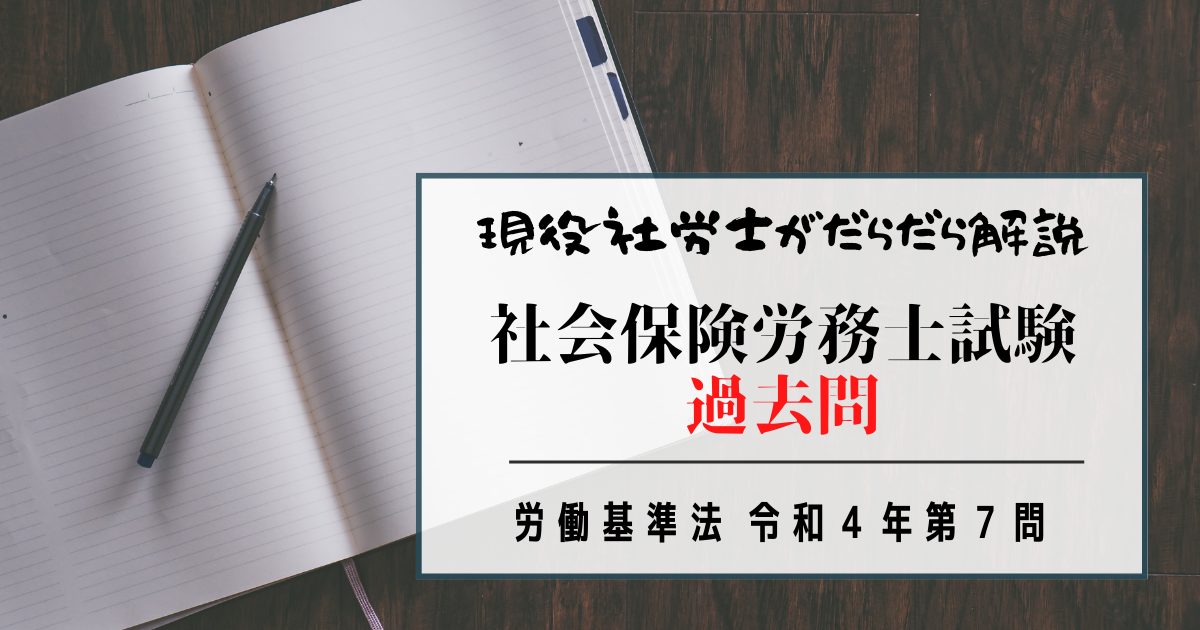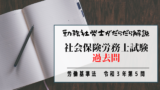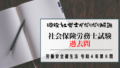労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
労働基準法 令和4年第7問 A
使用者は、労働基準法別表第1第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)、第10号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画の映写、演劇その他興行の事業)、第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)及び第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について48時間、1日について10時間まで労働させることができる。
則第25条の2第1項
根拠条文を確認します。
第二十五条の二 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。
労働基準法施行規則
本肢は、「労働時間の特例」に関する問題です。
労働時間の原則は、1日8時間・週40時間ですが、一部の法令に定められた業務については別途上限(週44時間)が定められています。
別途の定めとは、上記の根拠条文である「則第25条の2第1項」です。
●以下の対象事業において、常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
・ 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
・ 映画又は映写、演劇その他興行の事業(映画の製作の事業を除く。)
・ 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
・ 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
問題文には「48時間」とありますが、正しくは「44時間」となります。
本肢は×です。
労働基準法 令和4年第7問 B
労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を労使協定を締結することにより採用する場合、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ないときは1か月単位の変形労働時間制の効力が発生しない。
法第32条の2
根拠条文を確認します。
第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
労働基準法
② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
本肢は、「変形労働時間の協定」に関する問題です。
本肢は、労働時間の問題というより、労使協定のルールに関する問題と思います。
労使協定には…
①届出なければならないならない労使協定
②届出なければならず、さらに届出が効力発生要件となっている労使協定
があります。
①はとりあえず締結すれば届出しなくても有効は有効です(ただし「届出義務違反」にはなってしまいますが…)
②は、数ある労使協定の中でも36協定だけなのですが、届出をしていなければそもそも有効にもなっていない協定…となります。
ということで、今回の「1か月単位の変形労働時間制」に関する労使協定は①に該当し、締結すれば届出をしていなくても「有効か無効か」と言われれば「有効」となります。
なお、上記に書いた「①届け出なければならない労使協定」については、令和3年第5問Bの問題も参考になりますので、併せてご確認いただけると良いでしょう。
本肢は×です。
労働基準法 令和4年第7問 C
医療法人と医師との間の雇用契約において労働基準法第37条に定める時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていた場合、「本件合意は、上告人の医師としての業務の特質に照らして合理性があり、上告人が労務の提供について自らの裁量で律することができたことや上告人の給与額が相当高額であったこと等からも、労働者としての保護に欠けるおそれはないから、上告人の当該年俸のうち時間外労働等に対する割増金に当たる部分が明らかにされておらず、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができないからといって不都合はなく、当該年俸の支払により、時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということができる」とするのが、最高裁判所の判例である。
最判平成29年7月7日(医療法人康心会事件)
本肢は、「割増賃金」に関する問題です。
ベースは、上記「解答の根拠」にある判例ですので、一度お手持ちのテキスト等でご確認いただけると良いと思います。
まず、今回は先に正誤を示しておくと「×」となり、判例では…
(労働基準法第37条に定める時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意では)
・上告人に支払われた賃金のうち時間外労働等に対する割増賃金として支払われた金額を確定することすらできない
・通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することはできない
・上告人の時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金が支払われたということはできない
とされています。
今回の論点は、実務でもよく問題となる点です。
例えば(前提として、管理監督者ではなく、時間外労働・割増賃金の対象となる労働者をイメージしていただき)、雇用契約上で「月給50万円(時間外労働に対する割増賃金を含む)」というような記載がされていたとします。
結構、世の中の会社でも、上記のような記載をすれば割増賃金(残業代)を支払わなくてもOK!と考えている会社があります。
もちろん、上記のような「月給50万円(時間外労働に対する割増賃金を含む)」では、「基本給と残業代の境目がわからない/何時間相当でいくらぶんの割増賃金が50万円に含まれているのかがわからない」とされており、結果として、まったく残業代を払っていないとみなされてしまいます。
そのために、適切な合意の仕方としては、
・月給●万円(うち、▲時間の時間外労働に対する割増賃金◆円を含む)
というようにする必要があります。
労働基準法 令和4年第7問 D
労働基準法第37条第3項に基づくいわゆる代替休暇を与えることができる期間は、同法第33条又は同法第36条第1項の規定によって延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月以内の範囲内で、労使協定で定めた期間とされている。
則第19条の2第1項第3号
根拠条文を確認します。
第十九条の二 使用者は、法第三十七条第三項の協定(労使委員会の決議、労働時間等設定改善委員会の決議及び労働時間等設定改善法第七条の二に規定する労働時間等設定改善企業委員会の決議を含む。)をする場合には、次に掲げる事項について、協定しなければならない。
労働基準法施行規則
一 法第三十七条第三項の休暇(以下「代替休暇」という。)として与えることができる時間の時間数の算定方法
二 代替休暇の単位(一日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた一日又は半日を含む。)とする。)
三 代替休暇を与えることができる期間(法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた当該一箇月の末日の翌日から二箇月以内とする。)
本肢は、「代替休暇」に関する問題です。
法第37条第1項但書には、「1ヶ月に60時間を超える時間外労働をした場合の割増賃金」について「5割以上の割増率の割増賃金を支払わなければならない」と規定されています。
このように、通常の「2割5分」よりも高い割増率に設定することで、長時間の時間外労働を抑制すること狙っています。
そして、同条第3項には、当該割増賃金と休暇を相殺できる旨の規定があります。
表現は良くないですが、働かせすぎた分に対して、お金で報いるか休みで報いるか…というイメージです。
そして、休みで報いる!となった場合は、もちろん働かせすぎたタイミングから時間が空いた後に休みを与えても意味がありませんので、上記根拠で引用した施行規則にて、「2か月以内で労使協定で定めた時期に与えること」とされています。
本肢は○となり、本問の正解となります。
労働基準法 令和4年第7問 E
年次有給休暇の権利は、「労基法39条1、2項の要件が充足されることによつて法律上当然に労働者に生ずる権利ということはできず、労働者の請求をまつて始めて生ずるものと解すべき」であり、「年次〔有給〕休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』を要する」とするのが、最高裁判所の判例である。
最判昭和48年3月2日(白石営林署事件)
本肢は「年次有給休暇」に関する問題です。
会社員の方であれば、有給休暇を取得したことがある方が大半だと思います。
私の会社もそうですが、勤怠管理システムを導入している企業であれば、「この日に年次有給休暇を取得したい」とシステムで申請し、上司(勤怠管理者)がシステム上で「承認」ボタンを押す…というような感じの運用がされているのではないかと思います。
システムがない会社でも、紙の申請書を使っている…つまり、何らかの形での「申請➡承認」というスキームがある企業がほとんどでしょう。
では、その「承認」の段階で、上司(勤怠管理者)が「絶対に取らせない!!承認しない!!」となったら、有給休暇は取得できないのでしょうか。
つまり、上司(勤怠管理者)の承認は、有給休暇を取得するうえで絶対に必要なのか…という点について争われたのが、上記「解答の根拠」で引用した判例になります。
この判例によれば、「年次休暇の成立要件として「使用者の承認」という観念を容れる余地はない」とされています。
本肢は×です。